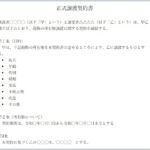犬猫の「保護ビジネス」
昨今しばしば耳にするようになりました。保護ビジネスというからには保護した動物を利用したビジネスになりますが、良し悪し含めて様々なものがあります。
例えば、里親募集は真っ先にあげられますし、保護犬・保護猫カフェも。保護犬を街頭に連れ出して募金活動をされるのも保護ビジネスの一環かもしれません。
また、芸能人の坂上忍氏はビジネスとして動物の保護活動を取り組まれたりしています。「保護ビジネス」と一口に言っても悪意や善意が入り混じっているのが現状なのかもしれません。
本記事では管理人が特にグレーだと感じている里親募集について、儲けの仕組みや動物愛護団体やペットショップ、保険会社の関係性、里親募集サイト上での実態などを踏まえて問題点を考察しました。
▼目次
- 保護ビジネスとは
- 儲けの仕組みとカラクリ
- ペットショップと動物愛護団体の関係
- ペット保険はどこの保険会社を指定されるのか?
- 保険の強制加入は保険業法違反では?
- フードの定期購入はどのメーカーのフードなのか?
- ゼロ円の無料譲渡にも問題がある
- 純血種は人気?飼い主の嗜好につけ込む
- ペットショップの譲渡活動と費用
- 保護ビジネスに加担しないために譲渡の際に確認したいこと
保護ビジネスとは
犬猫の保護ビジネスは様々な形態があるのは冒頭の通りです。その中で里親募集を行い譲渡先を探す形式の保護ビジネスについて考えてみます。
一般的に考えられているものは二通りあり、シンプルに考えると以下のような目的があります。
- 譲渡の際に経費や寄付金を請求し利益を得る営利目的のビジネス
- ブリーダーの繁殖引退犬猫やペットショップの売れ残りの処分を目的とするビジネス
どちらも動物の命や尊厳を軽視し、自分達の利益を追求することが目的です。また、どちらも犬猫の入手経路に特徴があります。
②の繁殖を引退したり売れ残りはわかりやすいくらいです。もはや「保護」された動物ですらないでしょう。①に関しては、保護を必要とする犬猫を対象に譲渡を行っている場合、活動資金は切実です。いくらかの運営費用を賄うために経費や寄付金を募って活動を続けているという団体なども多いと思います。しかしながらこちらで挙げた例はそうではありません。ブリーダーから無償(もしくは有償)で引き取った動物であったり、保護するにしても血統種しか扱わない(譲渡先が容易に決まりやすい犬猫のみに絞っている)などです。保護を必要とする動物を扱っているのではなく、容易に譲渡可能な利鞘を稼げる動物を対象にしているのが非倫理的と言わざるを得ないでしょう。
保護という言葉にビジネスを付けると途端に悪い印象を持ってしまいますが、保護を必要とする動物達を継続的に助けるためのビジネスならそこまで問題になる話ではないでしょう。当然そこには動物達のことを考えて必要な医療やケアを行っていく必要があります。動物を助けるのが目的ではなく、自分達の利益を追求することが問題なのだと思います。
儲けの仕組みとカラクリ
保護ビジネスの目的が営利目的の場合、一体どのように利益を得ているのでしょうか?里親募集サイトを利用していたとすると経費のみの請求となります。加えて寄付金を募るにしても限度額を設けているサイトもあります。一見、利益を得るには容易くないように思えます。
しかし、経費のみとしているものの、かかったとされる費用は掲載者が自由に決められます。例えばかかってもいない費用を請求することも可能ということです。(領収書や診断書、明細書といった書類の提出が不要であればに限ります)
ただし、医療費を例に考えてみると仮に領収書や診断書がなかったとしてもどちらの動物病院で診療したか、それはいつのなのかを聞かれたら病院に問い合わせれば確認が取れる可能性は高いです。このような安易な方法というより仕組みやカラクリといったものが存在すると考えられます。
①仕入れを有償(もしくは無償で)
通常は保護犬、保護猫なので当たり前ですが仕入れの費用(生体代)はかかりません。かかるとしても交通費などの輸送費用です。この辺りは掲載者の判断で経費として請求も可能です。(レスキュー時の交通費、輸送費などと称して)
しかし、ブリーダーやペットショップなどから繁殖引退犬や売れ残りを有償で引き取れば、利益の一部として確保できます。かつては『引き取り屋』と呼ばれる悪質な業者もいましたが、似たようなことをしていたとしてもちゃんと譲渡しているとなれば良し悪しの判断が難しくなります。
ブリーダーもペットショップも商売なので繁殖引退したり売れ残りはコストでしかありません。お金を払ってでも引き取ってもらいたいと考える経営者は少なからずいるということです。
他にも飼育困難になった飼い主から有償で引き取ることも同じようなことかもしれませんが、不定期な仕入れになると思います。ビジネスの観点で言えば継続して行うのは難しくレアケースだと思われます。
②フードの定期購入
譲渡の際にフードを定期購入させる掲載者がいます。フード代で稼ぐ方法は保護ビジネスに限った話ではなく、ペットショップでもよく使われる方法です。フード以外もペット用品などの購入も同様です。
それにしてもフードを買わせるとは一体どういうつもりでしょう?それもよりにもよってプレミアムフードを売りつけることが多い。人もそうですが犬や猫も食事は楽しみの一つです。なのになぜ勝手に食べ物を指定されなければいけないのでしょうか?しかも量まで決められて。飼い犬や飼い猫の好みでなかったらどうしたらいいんでしょう。途中解約も簡単にはできないことが多いです。とてもじゃありませんが飼い主や動物に寄り添ったサービスだと思えないのですが。買いに行く手間がかからない、フードを選ぶ必要がない、栄養は十分まかなえるなど利点もあるのは理解していますが、フードの定期購入自体がそもそも・・・と思ってしまいます。
③保険の強制加入
怪我や病気に遭った時に必要だから、高額な医療費も一定の金額が賄えるから。何かあった時に心配がいらないから。わからなくもありませんが余計なお世話という話も。
保険商品を契約してもらえれば紹介料を保険会社からいただけます。保険の加入が必須条件というのは、もはや単なる譲渡活動を超えているのは確かではないでしょうか?
④寄付金の強制徴収
寄付金は掲載者の裁量で里親から徴収することができます。経費ではないためそのままそっくり懐に入るという寸法です。
寄付金はいいと思います。愛護家や愛護団体の活動に賛同され、活動をサポートしたい里親本人の意思で寄付するのであれば。双方納得の上でもあります。
しかし、譲渡に寄付金の支払いが必須条件となるといかがでしょうか?
愛護家や愛護団体の活動に賛同したわけじゃないけど、保護犬、保護猫を引き取るために必要なので支払います。といった具合だったら保護動物を迎えようと考える飼い主の善意を利用した寄付金に成り下がってしまいます。
活動家からすると医療費も飼育費もかかります。すぐに飼い主が見つかるわけじゃなくて年単位でお世話している子もいます。仮に譲渡で10万円ほどいただいても赤字です。ということもよくある話かもしれませんが、それとこれとは別の話で飼い主の善意を利用するような寄付金はいかがなものかと思います。
寄付金が譲渡の必須条件で強制徴収というのは保護ビジネスに限らず違和感を覚える人もいらっしゃるのではないでしょうか?
ペットショップと動物愛護団体の関係
保護したとされる犬猫がペットショップの売れ残りかもしれないという話を聞きます。さらに、こんな噂話を聞くこともあります。
「ペットショップと動物愛護団体が組んで売れない犬猫を里親募集にかけている」
ありえなくない話です。しかし、本当にペットショップと動物愛護団体がグルのような話は表立っては聞かれないと思います。では、そのような不穏な関係性の動物愛護団体は存在するのか?という話です。
個人的に公表されている情報から幅広く探してはみましたが、繋がりがありそうではあるものの明確にできる程の情報はほとんどありませんでした。しかしながら、公表されている情報の一部を例にあげれば以下のようなことは確認できます。
- ペットショップを運営するオム・ファム(PETBOX)は、動物愛護団体などに支援金を提供。
- ペットショップを運営するアシストは、保護犬のためのOUENspace(応援スペース)を開設。保護犬・保護猫の譲渡の場として活用。
オム・ファム社は、沖縄県の会社で県内の動物愛護団体を支援しており、アシスト社は、ペットショップアシスト南国内にて動物愛護団体による譲渡会を開催していらっしゃいます。この他、Coo&RIKU社も動物愛護団体や医療施設へ寄付を行う活動をされています。対象の動物愛護団体名は公表されておりませんが、一部の動物愛護団体は寄付金のお礼などをSNSやホームページで公開されています。
また、ネット上である程度知られている話だと保護犬譲渡団体のアニフェアと高級ペットショップのペッツファースト繋がりです。アニフェアの代表が以前ペッツファーストの役員だったのではないか?という話ですが、明確に公表されている内容は現状確認できません。一部証拠の画像(会社概要の役員欄)も出回っておりますが確実な情報であるかは判断が付きませんでした。例えば、ペッツファーストの現役員の中に動物愛護に係わる活動をされている方がいるかなどはネットで検索をかければ分かるかもしれませんが、管理人が確認してみたところネット上では確認できませんでした。
大手ペットショップではCSV活動(社会貢献と事業活動の一環)を行っており、多くのペットショップで寄付や寄贈、募金活動しています。寄付先や寄贈先の詳しい情報は公表されないことが多いのですが、関係の深い動物愛護団体は少なからずあるでしょう。例えば保護ビジネスとまでは言えないもののブリーダーやペットショップから繁殖引退犬や猫、売れ残りの犬猫を引き取って里親募集をかけているところはあると思われます。純血種ばかり掲載されている場合は本当に保護した犬猫なのか疑問に思われる方がいてもおかしくないと思います。
ペット保険はどこの保険会社を指定されるのか?
ペット保険と言えば、アニコム損害保険が保険シェアNo.1を謳っており、続くのがアイペット損害保険、その後にペット&ファミリー損害保険と言われています。以前は、アニコム損保とアイペット損保でシェア70%程あるというお話を聞いたことがありましたが、現在は上位3社で70%超のシェアを占めているそうです。
となれば大方上記3社のいずれかを指定される可能性が高くなりますが、実際のところはどうなのでしょうか?実態を確認するために大手里親募集サイトで指定のペット保険の加入を条件としている掲載者を確認してみました。
※掲載者(保護団体、保護活動者)の名前は伏せ字にしています。
一般社団法人M -> アニコム損保、SBIプリズム少短動物愛護団体C -> 譲渡動物専用ペット保険(SBIプリズム少短)特定非営利活動法人A -> アニコム損保保護猫活動団体T -> アニコム損保一般社団法人U -> SBIプリズム少短
ペット保険の加入を条件としている掲載者の中で指定のペット保険の確認ができたものです。(里親募集の400頭程度を確認しています)SBIプリズム少短は、譲渡専用ペット保険「愛情ふるふる」の商品を扱っています。里親になるタイミングでのみ利用可能な保険となっております。また、アニコム損保は「どうぶつ健保きずな」もしくは「どうぶつ健保ふぁみりぃ」の商品だと思われます。特にきずなは、保護犬や保護猫でも加入できるペット保険のためこちらを指定されている掲載者も少なくないと思われます。
さて、ここまでの調べでアニコム損保、SBIプリズム少短が多く取り扱われているのがわかりました。では、ペット保険の紹介料や報酬を掲載者である保護団体や保護活動者は受け取っているのでしょうか?例えば、ペットショップとペット保険の会社間ではもちろんペットの販売時にペット保険を加入してもらうことでペットショップはペット保険会社からインセンティブを得ています。こちらは会社間で取り決めがあり営利関係の利害も一致するためよくある話だと思います。
一方、保護団体や保護活動者はどうでしょうか?
保険商品を扱うには少額短期保険募集人試験に合格する必要があり、通常であれば保険会社と代理店委託契約を結んでペット保険の商品を取り扱うと思われます。報酬は保険商品の販売価格の10~20%程度が相場だと考えられますがこの辺りは公表をされているわけではありませんので推測の域を脱しません。また、友達紹介キャンペーン等も各社が行っているためキャンペーンのポイントバックやキャッシュバックなどを受け取れる可能性もあります。
ペット保険の加入条件が必須で、指定のペット保険に加入する必要がある場合は掲載者に紹介料や報酬などが支払われている可能性が高いと思われます。
保険の強制加入は保険業法違反では?
そもそも保険を強制加入させられること自体、おかしいことなのでは?保険を加入するか、どのような保険を選ぶかは迎え入れる飼い主が考えて決めるのが本当は良いでしょう。譲渡条件に指定のペット保険の加入が含まれていることは納得しがたい方もおられると思います。
法律の観点で考えると
独占禁止法第19条 一般指定第10項 抱き合わせ販売保険業法第300条 第5項 特別利益の提供行為
この辺りが該当すると思われます。独占禁止法第19条の抱き合わせ販売は、ペットショップの販売の際も問題になったりします。犬猫を購入する条件として特定の保険に加入を強制することは「抱き合わせ販売」であり違法行為の可能性があります。譲渡する条件として特定の保険に加入を強制することも同様に法律違反である可能性が高いです。また、保険業法第300条の特別利益の提供行為は、保険に加入してくれたら本体価格を安くしますよ。と言った誘い文句は法律違反の可能性があるということです。譲渡でもペット保険を加入してくれたら譲渡費用を安くするといった話があれば同様の行為とみなされる可能性もあります。
いずれにせよ「強制」かどうかを掲載者である保護団体や保護活動者に聞いてみるのがいいでしょう。おそらく「強制ではありません」と答えられると思いますが、「強制です」と言われた場合は、掲載者との交渉より保険会社や消費者センターに連絡するのが手っ取り早いと思われます。(特に保険会社はよく分かっているので代理店契約先に事実確認をすぐに行ってくれると思います)
ここまでは、法律の観点に着目してみましたが、ペット保険の加入自体は悪いことではないと思います。特に保護犬、保護猫は素性(年齢や病歴、健康状態など)がはっきりしないこともあります。この場合、加入できるペット保険が限られてきますので保護犬猫でも加入ができたり特約が付いている保険であれば、その保険が適切であるかを判断して加入を検討するのがいいのだと思います。
フードの定期購入はどのメーカーのフードなのか?
フードに関しても定期購入を求める掲載者がいるのか?存在した場合、フードはどのメーカーを指定されるのかを確認してみました。確認方法はペット保険と同様です。大手里親募集サイトで掲載されている犬猫について確認しています。
※確認した里親募集サイトは「ペットのおうち」「ハグー」「いつでも里親募集中」「ペットのおうち」の4サイトです。
管理人が確認した結果、現時点(2025年3月)でフードの定期購入を求める掲載者はいませんでした。ただし、里親募集の終了した過去の譲渡を遡って調べてみると4件程確認できました。このうち3件は同じ保護団体。1件は別の保護活動者です。しかしながら里親募集ページ内にフードメーカーの記載まではなかったため正確なことはわからない結果となりました。
とはいえこれでは調べた内に入らないため出来る限りの調査をしてみた結果を記載して見たいと思います。
1件掲載のあった保護活動者の譲渡条件には「飼育費用として毎月5000円口座に振り込みます。キャットフードを定期的にお届けします」とありました。こちらはこれ以上のことはわかりませんでした。
また、3件の掲載のあった保護団体では「シェルター併設ショップから、1年間のフード定期便の購入をお願いいたします」とありました。こちらは保護団体の名前ももちろんわかっていますので、記載のあるシェルターや併設のショップを確認しています。ショップのサイトがあれば取扱いしているフードが分かるのでは?と思いましたがフードの掲載はなかったためわからず。それでは別の観点から保護団体がフードメーカーと手を組んでいないか、支援を受けていないかを調べてみるとこちらはヒットしました。とあるメーカーが当該保護団体に対しペットフードの支援を行った活動報告が確認できました。
とあるメーカー名は「ブッチ・ジャパン」無添加ドッグフード・キャットフードを手掛けられているニュージーランドが本社のメーカーです。
ただし分かったのはここまでで、上記メーカーはあくまで保護団体にペットフードの支援活動を行った実績があるというだけの話です。フード定期購入で指定していたかどうかまでは判明していませんので参考情報程度であることにご留意ください。
ゼロ円の無料譲渡にも問題がある
ゼロ円で無料で譲渡をしてしまうと安易に飼われる方にもらわれた場合、飼育放棄につながることがあります。
このため保護団体や保護活動家は様々な条件を付けて里親を探すことになりますが、その一つに譲渡費用も含まれています。ある程度の譲渡費用を支払えないような方はお断り、譲渡費用を支払ってでも保護動物を飼っていただけてその後の飼育も責任をもってしていただける方に引き取ってもらいたいという思いがあります。
保護動物は一度人間によって酷い目に遭った動物であることも少なくありません。このため里親に求めるものも多かれ少なかれあるのも理解できると思います。譲渡費用の請求は、終生飼養をしていただくための足きりのような側面もあります。
純血種は人気?飼い主の嗜好につけ込む
犬猫どちらも純血種は人気です。純血種はペットショップで購入を考えると種類にもよりますが数十万円することもあります。それに比べれば譲渡費用がかかったとしても比較的安くすむでしょう。加えて純血種を飼えるという欲求があれば満たせます。飼い主の嗜好ではありますが保護ビジネスを行っている側とすれば譲渡しやすいのがいいに決まっています。このため保健所から引き取る犬猫は血統種に限ってしまったり、募集中の純血種が実はサクラで応募したら飼い主が決まってしまったとか適当なことを言われて別の犬猫を紹介されるといったケースが出てきてしまいます。また、月齢が若い子も人気で飼い主が決まりやすいです。
純血種や月齢が若い子などが人気なのは当然のことかもしれませんが、何らかの事情や問題があって保護された犬猫の譲渡という主旨を考えると純血種だから子犬だから子猫だから、可愛いからといった理由だとすれば里親になる飼い主の嗜好にも少し問題があるのかもしれません。
ペットショップの譲渡活動と費用
大手ペットショップでもCSR活動(社会貢献と事業活動の一環)として犬猫の譲渡活動を行っているところもあります。
例えば、Coo&RIKU(クーアンドリク)やペッツファーストは犬猫の譲渡活動を行っておりますが、譲渡をゼロ円で受けられるわけではありません。
Coo&RIKUの譲渡費用
譲渡負担金はかからないとしていますが、生体費用がかからないだけで諸経費はかかります。
| Fam(迷子捜索サポート登録料) | 1,320円 |
|---|---|
| 年会費5年分 | 2,750円 |
| 譲渡犬猫ケアパック | 33,000円 |
| 総額 | 37,070円(税込) |
一番高額な譲渡犬猫ケアパックは、予防接種を何年かに渡って無料で受けられるケアサービスのようです。この他の費用として、フード定期購入の代金とペット保険の保険料が発生します。フードは、1歳以上が3年間、1歳未満が5年間の契約となり犬と猫、サイズによりフードの量は変わってきますが、一ヵ月3,000~5,000円程度はかかってくるようです。ペット保険の保険料は公開されていないため不明です。
ペッツファーストの譲渡費用
ペッツファーストの諸経費は公式HPで金額は明示されていません。以下は譲渡条件の中から経費としてかかるものを羅列したものです。
- ほっとサポート加入
- ペット保険
- 各種ショッピングローンクレジット
ほっとさぽーとは、通常の生体販売でも加入を勧められているものです。主に健康面のサポートをしてくれるサービスとなっています。ペット保険については、詳しい情報の記載はありませんがこちらも保険に入るのが条件になっているようです。この他、各種ショッピングローンクレジット申込書への記載とありましたが、確認したところ譲渡の場合は現金もしくはクレジット決済のためショッピングローンの申し込みは不要とのことでした。また、病気の予兆(下痢・嘔吐・食欲不振等)が確認された場合、ペッツファーストに連絡することなども記載されていますが、こちらはほっとさぽーとへの加入もありますのでご病気の際はご相談をといったものと思われます。
ペットショップが行う譲渡活動では、生体に値段が付いているということはありませんが、諸経費は一般的な里親募集と同じようにかかるようです。
保護ビジネスに加担しないために譲渡の際に確認したいこと
前述したように保護ビジネスなのかを判断するポイントはあります。
- 純血種ばかりを扱っている。
- 雌が多い。
- 繁殖引退の子が多い。
- 保険加入が必須。
- フード購入が必須。
- 寄付金が高い。
純血種は特に猫の場合は要注意かもしれません。野良猫を見て分かるように、キジトラ、茶トラ、黒猫や白猫などの雑種が多く純血種はほとんど見られません。保護される猫も雑種が多いためブリーダー放棄など理由が明らかである以外は入手経路は要確認だと思います。また、繁殖引退の子は雌の方が多いのでこの辺りも注目してもいいかもしれません。保険加入やフード購入はあまり散見はされないかもしれませんが、見かけたら避けておくのがいいのだと思います。
この他、譲渡にかかる経費について領収書や診断書などがない、トライアル期間がなく飼育に関する条件が設けられていない(お金を出せば誰でも譲渡OK)なども動物福祉の観点で考えると疑問が生じると思います。
保護された経緯や出産歴、病歴など確認できる点は事前に確認し、譲渡費用に納得できたら里親になるか検討するのがいいのだと思います。
以上になります。今のご時世、情報化社会でありSNSも普及していることもあり、悪質な保護団体はさらされやすくなったと思います。このため誰が見ても明らかなケースは少ないのかもしれません。いずれにせよ飼い主になったらその子と長い期間を過ごすことになります。なるべくその子の出自など気になる情報は知りたいものですね。納得できなかったり腑に落ちない場合はきちんと確認してから飼い主になるのが良さそうです。